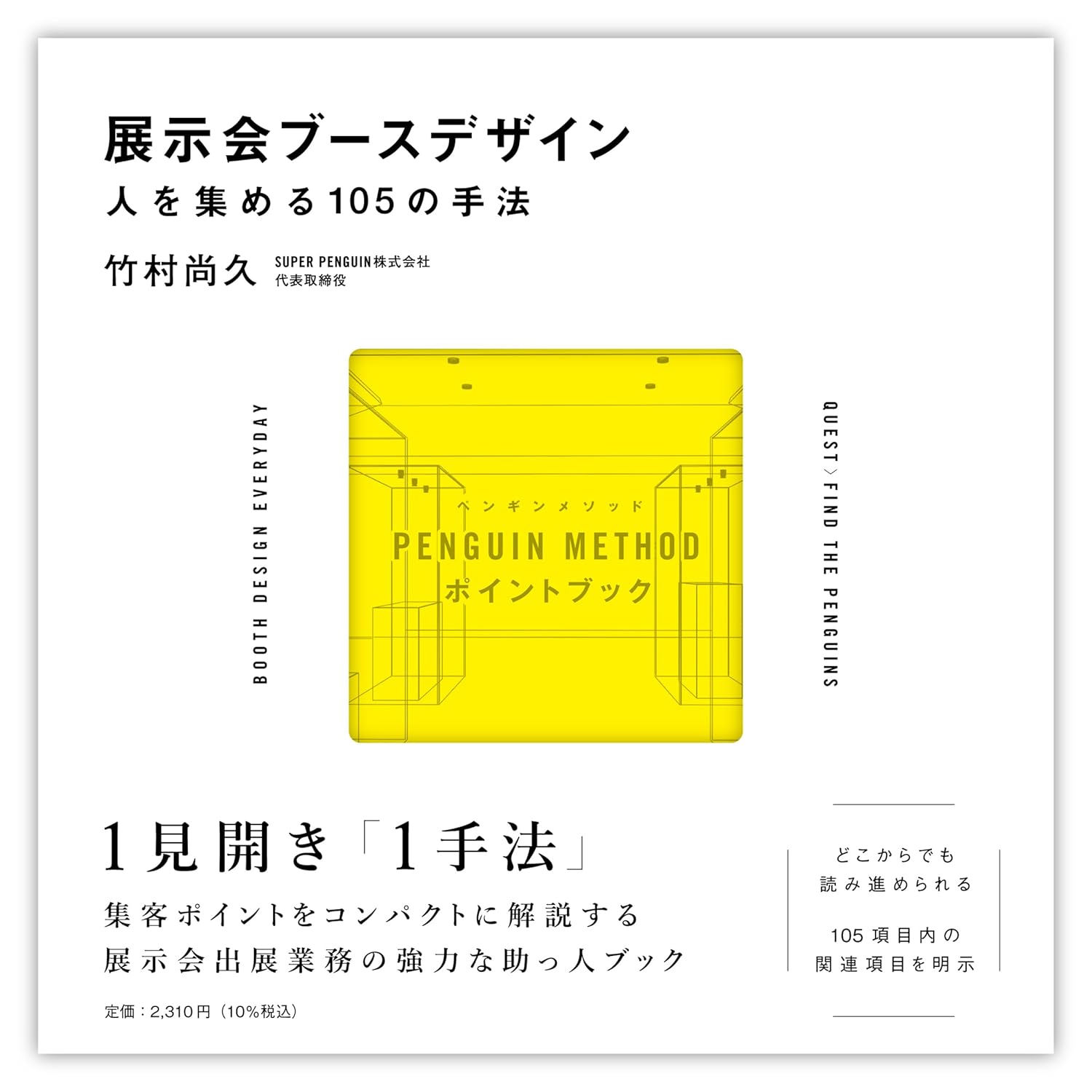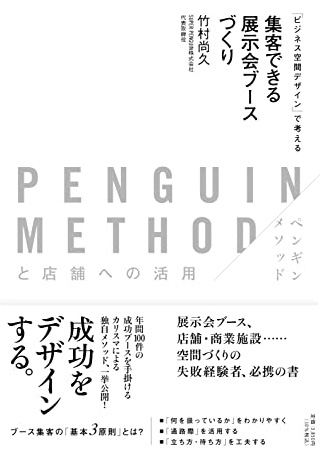ブース検討の流れ
ブースを考える際には、いきなり詳細のレイアウトを考えるべきではありません。まず、会場図(小間位置図)を見て、来場者がどのように動くのか、自社ブースの位置にどちらから近づいてくるのか、どこからよく見えるのかを俯瞰して考えます。そうすると、ブースの基本形状が見えてきます。その基本形状が見えてきてから初めて詳細な部分を検討していくと効果的なブースに近づいてきます。
下記はおおよその検討順序になります。もちろん実際には様々なことを同時に考えていかなければいけませんが、まず条件や情報を整理し、会場全体からの「大きな視点」で考えること。その上で詳細な部分を検討していくという流れになります。ただ、人は一方のことに集中すると他方がおろそかになりますので、時折大きな視点に立ち戻り、大きな視点、小さな視点を行き来しながら検討を進めていく必要があります。
検討の順序
- 1. 1分間説明を検討してみる
- 2. 小間位置図上で、会場全体を俯瞰しながら人の流れを予測する
- 3. 小間位置図上で、キャッチの言葉の位置、展示台の位置を決定する
- 4. 2で決めた大きな配置をベースとして、ブースのレイアウトを検討する
- 5. 1で考えた1分間説明をベースにキャッチの言葉を検討する
- 6. 展示台の上の陳列を考える
- 7. スタッフの立ち位置を考える
5つのキーワード
1. 1分間説明
ブースに何を出展するか、来場者に何を伝えたいか、どんな言葉をキャッチにすればいいのか、迷った時には、1分間説明をまず作ることをお勧めします。会期中、ブースの前に立った時に、通りかかった来場者に 1分間で何かを説明するとしたら、どんなことを話しますか? 1分間で説明をまとめることは意外と難しいもの。このまとめている過程で何を伝えればいいのかがはっきりしています。また、キャッチの言葉もここから導き出すとよいでしょう。
2.遠目と近目を使い分ける
ブース検討に際しては、ブースの 30m前、10m前、5m前、目の前、など来場者の目線に立ってその見え方を考える必要があります。例えば 30m前からどう見えるか。5m前に来た時に、他のブースよりもこちらのブースに寄っていただくためにはどうするか、目の前に来た時、ブースの商品を手に取っていただくにはどうするか。このように遠くから見る目線の「遠目」と近くから見る目線の「近目」を使い分けて考えるようにします。
3.会話のきっかけをつくっておく
来場者がブースに立ち寄っていただいた時、どのようにお声掛けするべきでしょう。展示会に出展される方は店舗の販売員のような経験がない方がほとんど。お声掛けしようにもタイミングが難しい場合があります。でも、来場者の方から「これは何ですか」などのお声掛けを逆にしていただけたら、自然な形で会話がはじめられます。そのためにはブース内に「気になるもの」を置いておくと効果的です。できれば営業会話のきっかけになるようなものならベストです。
4.滞留させる工夫をする
ブースに来場者がいなくてスタッフだけが待ち構えている。そんなブースには来場者はなかなか近づけないものです。しかし、数名でも来場者がブース内にいると安心して近づくことができます。そのためにブース内に「滞留時間が長くなるポイント」を作っておくと効果的です。例えば、何かの作業をしてもらう、体験をしてもらうなど商品・サービスを知ってもらう上で有効なものを置いておきます。
5.五感で感じてもらう
商品を陳列する際には、出来るだけ五感で感じられるように置くと効果的です。「見る」だけではなく、手に取って実際に触れることができるようにすること。よくケースの中に商品を置く場合があります。高級感を出すという意味では有効な手段ですが、来場者にとっては「見る」という行動しかできないため、あまり強く意識には残らないと考えるべきです。手に取ってしっかり感じて帰っていただいた場合、後日になって「あの時の・・」と思い返す率を高めることができるのです。五感で感じて帰っていただき後日想起してもらうこと。商品の陳列で大事な考え方の 1つです.
本記事の監修者について

- SUPER PENGUIN株式会社代表取締役|展示会プロデューサー/デザイナー
- 兵庫県姫路市生まれ。法政大学大学院工学研究科建設工学専攻修了。一級建築士。1996年4月・五洋建設株式会社入社。2005年6月・インテリアデザイン事務所ディーコンセプトデザインオフィス(現・SUPER PENGUIN株式会社)設立。2006年5月・東京インテリアプランナー協会 理事就任 / インテリア系展示会IPEC/JAPANTEX実行委員会。2008年5月・東京インテリアプランナー協会 副会長就任 / インテリア系展示会IPEC/JAPANTEX実行委員会。2012年9月東京造形大学 非常勤講師(~2018)
最新の投稿
 2026年2月18日メルマガ登録ありがとうございました。
2026年2月18日メルマガ登録ありがとうございました。 2025年10月28日業種ごとに抑えるべき展示ブースのポイント
2025年10月28日業種ごとに抑えるべき展示ブースのポイント 2025年10月28日人の集まりに波があるときの対処法とは
2025年10月28日人の集まりに波があるときの対処法とは 2025年10月28日展示会ブース出展における最小限のチェックリスト
2025年10月28日展示会ブース出展における最小限のチェックリスト
PENGUIN METHOD ~結果を出す集客手法~
- 1-1 展示ブースに人が集まらない5つの理由
- 1-2 展示会出展に成功するとは?
- 1-3 展示会ブースに必要なものとは?
- 1-4 展示会ブース検討の基本概念
- 1-5 ブースデザイン検討の前提条件
- 1-6 理想的なブースとは?
- 1-7 ブース検討の流れと5つのキーワード
- Point 01. 小間位置を分析する
- Point 02. キャッチの言葉の考え方
- Point 03. 通路際を活用する
- Point 04. 照明を効果的に使う
- Point 05. 陳列を検討するポイント
- Point 06. 収納の考え方
- Point 07. 商談席の考え方
- Point 08. ブースイメージの決定方針
- Point 09. パネルデザインと配布物
- Point 10. スタッフ配置戦略
- 人の集まりに波があるときの対処法とは
- 展示会ブース出展における最小限のチェックリスト
- 業種ごとに抑えるべき展示ブースのポイント